說一切有部の成立に関する考察 : หน้า 3/35
การกำเนิดนิกายสรวาสติวาท (1) : หน้า 3/35 本稿では說一切有部の名称の由来とその教理の発展について考察します。
0 ครั้ง
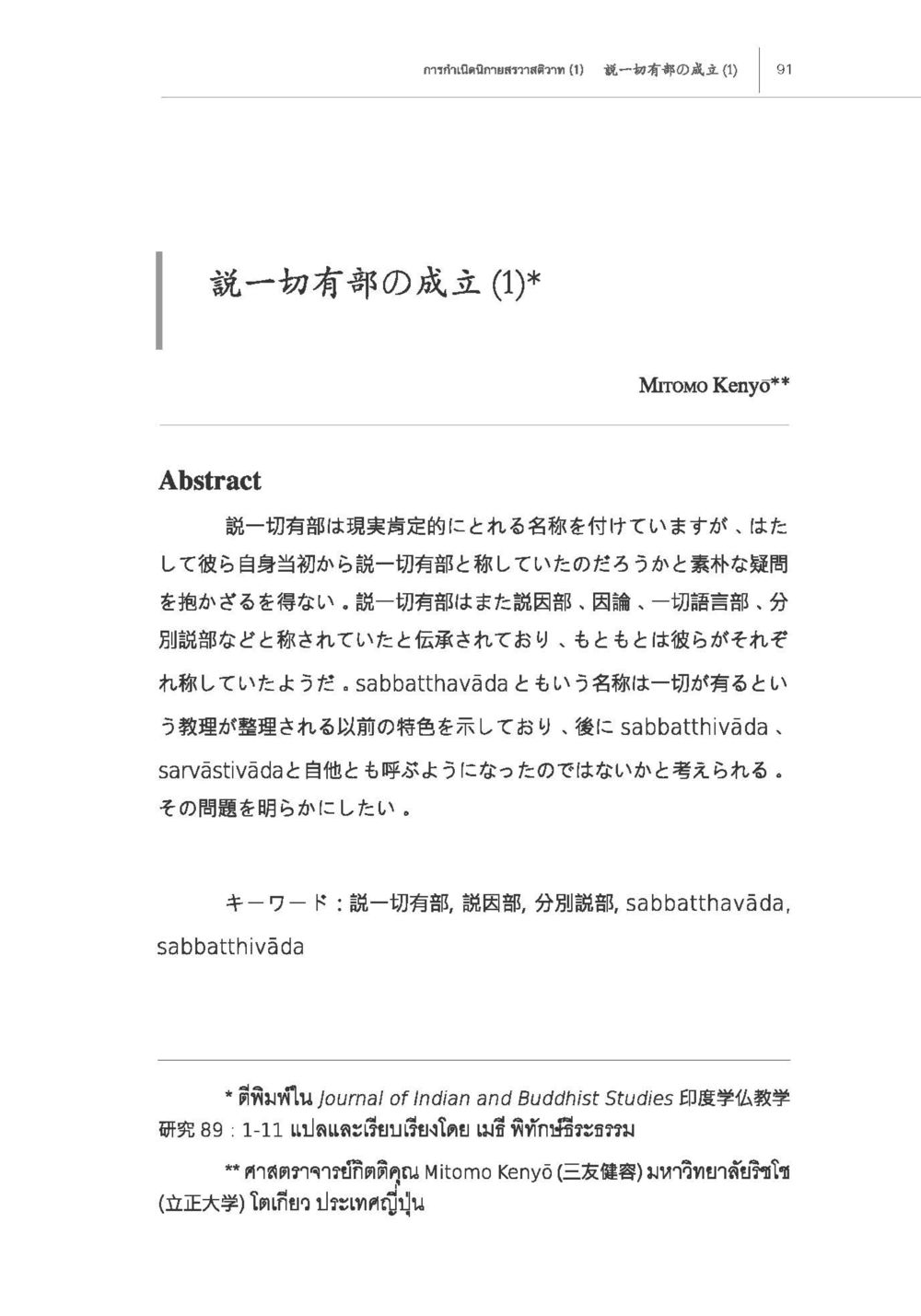
สรุปเนื้อหา
本論文は、說一切有部の名称についての考察から始まり、彼らが他にどう称されていたかを探ります。また、sabatthavādaという名称がどのように発展したのか、その背後にある教理を整理する過程を明らかにしたいと思います。彼自身が初めからこの名称を使用していたのか、歴史的な背景についても考察します。sabatthavādaは物事が存在するという教理の特徴を示しており、その後の呼称についての議論も行います。本研究は、これらの名称がどのように変遷してきたか、またそれが何を意味するのかを明らかにすることを目指しています。
หัวข้อประเด็น
- 說一切有部の名称の由来
- 論理的背景
- sabatthavādaの教理の発展
- 歴史的考察
ข้อความต้นฉบับในหน้า
說一切有部の成立(1)*
MITOMO Kenyo**
Abstract
說一切有部は現実肯定的にとられる名称を付けていますが、はたして彼自身当初から說一切有部と称していたのだろうかと素朴な疑問を抱かざるを得ない。說一切有部はまた說因部、因語部、一切語部、分別說部などと称されていたと伝承されており、もともとは彼らがそれぞれ稱していたようだ。sabatthavādaという名称は一切が有るという教理が整理される以前の特色を示しており、後に sabbatthivāda、sarvātivādaと自他とも呼ぶようになったのではないかと考えられる。その問題を明らかにしたい。
キーワード:說一切有部、說因部、分別說部、 sabatthavāda、 sabbatthivāda
*(英語訳:* ตำราพินิจ Journal of Indian and Buddhist Studies インド学仏教学 研究 89 : 1-11 แปลและเรียบเรียงโดย เมธี พุทธสิริธรรม
**(英語訳:** คาสตราจารย์กิตติคุณ Mitomo Kenyo (三友健容) มหาวิทยาลัยรัชโซ โคเชียว ประเทศญี่ปุ่น
Tags : #說一切有部 #說因部 #分別說部 #sabatthavāda #sabbatthivāda
หนังสือที่เกี่ยวข้อง
Load More



































